目次
所有する土地の相続を考えている方のなかには、土地を子ではなく孫に直接相続させたい方もいるでしょう。
基本的に、祖父母の土地を孫に直接相続させることはできません。そのため、土地を孫に相続させたいのなら、相続以外の方法を検討する必要があります。具体的には「生前贈与」や「死因贈与」などです。
今回は、祖父母の土地を孫名義にする方法と注意点を解説します。所有している土地を孫に相続させたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
祖父母から孫への土地相続は原則としてできない

相続には、大きく分けて法定相続と遺言相続の2つの種類があります。遺言書がある場合は遺言書の内容にしたがって相続(遺言相続)しますが、遺言書がない場合は民法の規定にしたがいます(法定相続)。
民法で定められているのは、法定相続における相続人の範囲や順位、相続分です。
法定相続の対象となる相続人の順位は配偶者(必ず相続人)、被相続人の子(第1順位)、被相続人の父母(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)です。第2順位の人は第1順位、第3順位の人は第2順位の人がいない時に相続人になれる仕組みとなっています。
基本的に孫は祖父母の法定相続人にはなれません。ただし、代襲相続や再転相続する場合は孫が祖父母の法定相続人となります。
| 代襲相続 | 本来相続人となっている方が、相続開始時点で死亡している場合、その人の子などが代わって相続人になる制度。 |
|---|---|
| 再転相続 | 相続人となっている方が、相続の承認や放棄をする前に死亡した場合、その人の子などが代わって相続人になる制度。 |
祖父母の土地を孫が相続するための方法4つ

祖父母の土地を孫名義にする方法には、「生前贈与」「死因贈与」「養子縁組」「遺言書による遺贈」の4つがあります。それぞれメリット・デメリットがあるため、特徴をふまえて最適な方法を選択しましょう。
生前贈与
生前贈与は、祖父母が生きている間に、土地を無償で孫に譲渡する方法です。贈与する相手とタイミングを選べるほか、基礎控除や相続時精算課税制度により贈与税の負担を軽減できる可能性があります。贈与した分、相続時の財産が減るため相続税の負担軽減も期待できます。
贈与に対する課税制度は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類です。それぞれ税額の算出方法や非課税枠の上限が異なります。
| 概要 | メリット・デメリット | |
|---|---|---|
| 暦年課税制度 | 贈与した額に対する課税方法。 1年間の贈与額を計算し、贈与額から基礎控除を差し引いた課税価格に税率をかけて税額を計算する。 |
〈メリット〉 ・年間110万円の基礎控除がある ・何度も贈与できる 〈デメリット〉 ・多額の贈与には向かない ・制度利用に手続きが必要 |
| 相続時精算課税制度 | 60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に利用できる制度。制度を利用することで、贈与税の計算の際に控除を受けられる。 | 〈メリット〉 ・基礎控除(年間110万円)と特別控除(限度額2,500万円)がある ・控除額の2,500万円を超過した分の贈与税の税率が一律20%になる 〈デメリット〉 ・一度選択すると暦年課税制度を使えなくなる ・制度利用に手続きが必要 |
生前贈与のメリット・デメリットについては、以下の記事でより詳しく解説しています。併せてご覧ください。
死因贈与
死因贈与は、祖父母の死を条件とした贈与契約です。遺言による遺贈も祖父母の死を起因としていますが、遺言が被相続人の一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の双方の合意が必要になります。
死因贈与は口頭でも成立しますが、トラブルを回避するために公正証書にしておくのがおすすめです。また、死因贈与する場合は不動産の仮登記が可能です。遺贈では仮登記できないため、権利を保全したい場合は死因贈与が向いています。
なお、死因贈与は贈与税ではなく相続税の対象です。贈与に際して登録免許税と不動産取得税もかかるため、納税の準備をしておきましょう。
相続登記の登録免許税の基礎知識|計算・納付方法や免税措置を紹介
養子縁組
祖父母と孫で養子縁組する方法です。養子縁組することで孫が実子と同等の相続権を持つことになります。相続人の数が多くなることで相続税の基礎控除額、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増えるメリットもあります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
生命保険・退職手当金の非課税額=500万円×法定相続人の数
ただし、法定相続人に含められる養子は祖父母に実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までです。
また、財産を相続した人が配偶者や父母、子以外の場合、相続税が2割加算される点にも注意が必要です。養子縁組したらかえって相続税が増えたとならないよう、手続きする前にかかる税金を算出しておきましょう。
遺言書による遺贈
遺言書を作成して孫に土地を贈与する方法です。被相続人が遺言書で財産と取得する人を指定することで、孫が土地を相続できます。
ただし、遺贈では相続で不動産を取得するよりも税金の割合が高くなる点に注意が必要です。
| 遺贈 | 相続 | |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 法定相続人:非課税 法定相続人以外(包括遺贈):非課税 法定相続人以外(特定遺贈):土地・住宅3.0% |
非課税 |
| 登録免許税 | 法定相続人:0.4% 法定相続人以外:2.0% |
0.4% |
なお、遺言による贈与では、死因贈与と異なり相続放棄される可能性があります。指定した相手に確実に財産を渡せるわけではない点に注意しましょう。
祖父母の土地を孫が相続する際の注意点
祖父母の土地を孫名義にする際は、以下の2つの点に注意しましょう。
- ほかの相続人とよく話し合う
- 専門家に相談しながら手続きする
ほかの相続人とよく話し合う
祖父母の土地を孫に相続させることで、ほかの相続人の相続財産が減ってしまう場合があります。相続人同士でよく話し合わずに手続きを進めてしまうと、軋轢が生まれてしまうかもしれません。
また、相続人にはそれぞれ遺留分(最低限保証される相続財産)がある点にも注意が必要です。もし孫に土地を相続させることでほかの相続人の遺留分を侵害する際には遺留分侵害額請求をされる場合があり、孫に余計な気苦労をかけてしまいかねません。誰がどの財産を相続するかなど、法定相続人との協議を重ねて合意を得たうえで手続きしましょう。
専門家に相談しながら手続きする
祖父母から孫へ土地を相続するにあたり、どのような手法をとるべきかはケースによって異なります。個人で調べてみても判断できない場合もあるため、相続に詳しい専門家に相談しながら最適な手法を探っていきましょう。
また、相続に関する手続きや税計算は複雑です。司法書士や弁護士、税理士、行政書士などに相談して、スムーズに手続きを終えられるよう準備を進めていきましょう。
まとめ
孫は祖父母の法定相続人に含まれないため、原則土地を相続させることはできません。しかし生前贈与や死因贈与、養子縁組、遺言による遺贈などの手法を使えば、孫へ財産を残せます。各手法のメリット・デメリットをふまえて最善の方法を検討しましょう。
相続にあたっては、ほかの相続人とも十分に話し合う必要があります。財産を巡って親族間で争いが起きないよう、慎重に合意形成していきましょう。
土地を孫にスムーズに相続させたいなら、相続の専門家が在籍する一誠商事へご相談ください。地域密着型の不動産会社として、茨城県南・県央や東京エリアで事業を展開する一誠商事なら、不動産のプロとして土地相続の悩みに寄り添えます。また、土地活用についても相談を受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
事前の対策から相続後の対応まで、
様々な相続問題をサポートします。
土地や建物など、分けることが難しい「不動産」の相続財産について、
不動産の知識を豊富に有した当社が、不動産相続をご支援
させていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

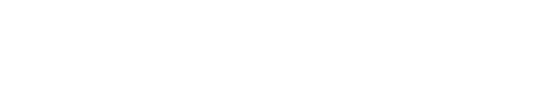
記事の監修者:一誠商事編集部
一誠商事株式会社が運営する情報サイト編集部。
不動産売買・賃貸経営・土地活用・不動産相続から快適な暮らしや住まいのことまで、不動産に関する幅広いお役立ち情報を発信しています。
創業50年、茨城県南・県央エリアで
地域密着型の不動産会社
一誠商事は、創業50年を迎えた地域密着型の不動産会社です。賃貸・管理・売買・保険・リフォームを取り扱っており、お客様のお悩み事をワンストップで解決いたします。
所有しているアパート・マンションの空室が多くて困っている、空き家の管理を依頼したい、自宅を売却したい、住み替えを検討している等、不動産に関することならなんでもご相談ください。













