不動産の所有者が亡くなり、土地や建物を相続する際には、相続登記をする必要があります。相続登記手続きで発生する費用の一つが、「登録免許税」です。
この記事では、相続登記の登録免許税の基礎知識として、登録免許税額の計算方法や納付方法、例外的な免税措置などを解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも「相続登記」・「登録免許税」とは?
まずは、相続登記と登録免許税の概要を解説します。
相続登記の概要
相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった際に、従来の所有者から相続人へ不動産の名義を変更することです。「相続による所有権の移転登記」をすることを、一般的に「相続登記」と呼びます。
相続登記は、2024(令和6)年4月1日から義務化されました。相続人は、不動産を相続したことを知った日から、3年以内に手続きをしなければなりません。
その背景には、登記簿から所有者を特定できない「所有者不明土地」が全国的に増加し、放置されることで周辺環境が悪化するといった社会問題が挙げられます。
また、相続登記をしていなければ、関係者間で所有権に関するトラブルが起こる可能性もあるでしょう。
なお、相続登記の義務化について詳しくは、以下の記事で解説しています。
相続登記の義務化はいつから?費用・手続きの流れや、登記できない時の対処法も解説
また、土地や建物の相続登記について知りたい場合には、以下の各記事もぜひ参考にしてください。
親から子へ土地を名義変更する方法|生前贈与・相続時の税金や節税方法も
亡くなった親名義の家|名義変更の必要性や費用、必要書類について解説
登録免許税の概要
登録免許税とは、不動産や会社、人の資格などについての登記等をする際に課される税金のことです。例えば、土地と建物の両方を相続した場合は、土地と建物それぞれに登録免許税がかかります。
相続登記の登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。ただし、相続人以外の人が遺言に基づき相続登記をする際の税率は、固定資産税評価額の2%と定められています。
なお、相続登記において、登録免許税と相続税は別物である点に注意が必要です。
宅地の評価方法は?相続税の減額につながる土地の特徴などを解説
自宅を相続したら税金はかかる?相続税を減額できる特例とその適用条件
相続登記の登録免許税の免税措置

以下のケースに当てはまる場合は、租税特別措置法に基づく特例として、相続登記の登録免許税は免除されます。
- 土地の相続人が相続登記をする前に亡くなった場合
- 相続する土地の価額が100万円以下の場合
ただし、この免税措置の適用期限は、現時点で2025(令和7)年3月31日までです。適用期限の延長有無や内容変更など、今後の動向に注目する必要があります。
相続登記の登録免許税を計算する流れ
ここでは、登録免許税の計算方法を見ていきましょう。
1.固定資産税評価額を調べる
固定資産税評価額は、毎年4月~6月頃に送られてくる、最新の固定資産課税明細書で確認可能です。
固定資産課税明細書が見つからない場合には、不動産所在地の市区町村役場において、固定資産評価証明書(価格通知書)を取得して調べる方法もあります。
固定資産課税明細書や固定資産評価証明書に、「評価額」または「価格」と記載されている箇所をチェックしましょう。
2.課税標準額を算出する
亡くなった方が不動産を誰かと共有していた場合は、調べた固定資産税評価額に持分をかけます。例えば、固定資産税評価額が2,000万円、持分が2分の1の場合、対象となるのは1,000万円です。
そのうえで、相続登記をする不動産の評価額を合計したら、1,000円未満を切り捨てます。これが「課税標準額」です。
なお、不動産の共有持分について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
不動産の共有持分は贈与・放棄できる?贈与税など発生する税金も解説
3.登録免許税率をかける
先述のとおり、登録免許税の基本の税率は0.4%です。求めた課税標準額に0.4%をかければ、登録免許税額を算出できます。
最後に、100円未満を切り捨てることを忘れないようにしましょう。
ただし、算出した登録免許税額が1,000円未満の場合、支払うべき登録免許税は1,000円となります。
相続登記の登録免許税の納付方法
登録免許税は、相続登記を申請するタイミングで支払う必要があります。その際の納付方法は、大きく分けて「現金」・「収入印紙」・「キャッシュレス」の3つです。
参考:登録免許税のあらまし|国税庁
現金で納付する
現金での納付を選択する場合は、法務局にて直接現金払いをすることはできないため、金融機関で納付書をもとに登録免許税を支払います。
その際、領収証書(領収済通知書)が発行されるので、登記申請書に貼り付けて法務局に提出しましょう。
収入印紙で納付する
登録免許税額が3万円以下の場合などには、収入印紙による納付が可能です。郵便局などで収入印紙を購入し、登記申請書に貼り付けて提出します。
この時、収入印紙には割印(消印)はしないようにしましょう。
キャッシュレスで納付する
キャッシュレス納付として、インターネットバンキングやクレジットカードでの納付もできます。キャッシュレス納付は、忙しい方におすすめの方法です。
利用できるクレジットカードは、本人認証サービスの「3Dセキュア」を採用しているものに限られます。登録免許税額に2.2%をかけた、決済手数料を負担する必要がある点に注意してください。
相続登記で登録免許税以外にかかる費用

最後に、登録免許税以外に把握しておくべき、相続登記をする際にかかる費用を紹介します。
関係書類の発行手数料
相続登記の際には、以下のような書類が必要です。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 不動産登記事項証明書 など
これらの書類の発行には、一定の手数料がかかります。一つひとつの発行手数料は1,000円に満たなくても、全体で1~2万円程度になることは珍しくありません。
特に、複雑な相続のケースでは、費用がかさみやすいでしょう。
司法書士への報酬
相続登記をスムーズに進めるために、司法書士へ依頼するケースも多いかもしれません。この場合は、司法書士に支払う報酬も考慮しておきましょう。
報酬の目安は5~15万円程度ですが、設定金額は自由化されており、地域や相続関係の複雑さなどによってもバラつきがあります。事前に見積書の作成を依頼し、金額に納得したうえで契約することが大切です。
まとめ
土地や建物などの不動産の所有者が亡くなり、相続登記をする際には、原則として登録免許税の支払いが生じます。
まずは不動産の固定資産税評価額を調べ、登録免許税額を算出してみましょう。登録免許税は、現金やキャッシュレスなど、任意の方法で納付可能です。
不動産会社の一誠商事には、「相続の専門家」として、認定相続コンサルタントが在籍しています。不動産を相続することになりお困りの方や、将来の相続に不安を抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
事前の対策から相続後の対応まで、
様々な相続問題をサポートします。
土地や建物など、分けることが難しい「不動産」の相続財産について、
不動産の知識を豊富に有した当社が、不動産相続をご支援
させていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

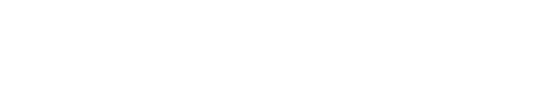
記事の監修者:一誠商事編集部
一誠商事株式会社が運営する情報サイト編集部。
不動産売買・賃貸経営・土地活用・不動産相続から快適な暮らしや住まいのことまで、不動産に関する幅広いお役立ち情報を発信しています。
創業50年、茨城県南・県央エリアで
地域密着型の不動産会社
一誠商事は、創業50年を迎えた地域密着型の不動産会社です。賃貸・管理・売買・保険・リフォームを取り扱っており、お客様のお悩み事をワンストップで解決いたします。
所有しているアパート・マンションの空室が多くて困っている、空き家の管理を依頼したい、自宅を売却したい、住み替えを検討している等、不動産に関することならなんでもご相談ください。









